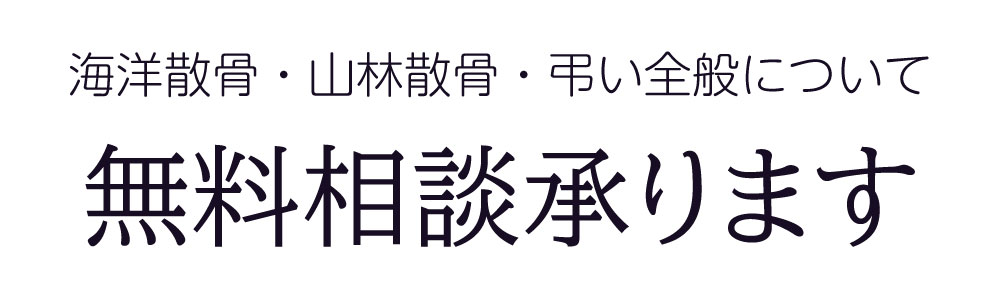普段の生活のなかで、「死」について考えることはどれくらいあるでしょうか?人間は死すべきものです。普段私たちはそのことを意識することなく生きています。私たちはみな死を迎える存在でありながら、健康で日々の生活に追われていると、その事実に意識が向かなくなってしまうことがあります。さしせまった状況に置かれるまでは考えたくないという思いも理解できます。しかし、それは生きていることの「真実」からの逃避ではないのでしょうか。その証拠に、いざ死というものが自分のこととして頭をもたげると、不安や焦りが急に襲ってきます。
多くの文化は死に向き合って生きるような仕組みをもっていました。成熟するとは、「生と死の文化」を身につけ、自覚を深めていくことでもありました。ところが、近代の実利主義的な文化や学問では「生と死の文化」を遠ざけてきたのも事実です。それは、病院のように生命期間を伸ばすための医療現場だけでなく、ホスピスのような死にゆく人のケアの現場においてさえそうでした。
東京大学では、「生命倫理は死生観を反映する」として、脳死・臓器移植、安楽死、人工妊娠中絶、生殖補助医療、出生前診断・着手前診断に対する受け止め方がどのように異なるか、その背景にある宗教観とともに研究されています。
日本人の宗教観の特徴のひとつは、それが「アニミズム」に根付いていることです。「アニミズム」とは、人間だけでなく、動植物や無生物など全てのものに魂があるとする考え方。たとえば、「本を踏んづける」という行為に抵抗感を覚えないでしょうか? このような抵抗感は、ものに魂を見出すアニミズムの思想に通底する感覚です。日本のような多神教の国では、アニミズムが宗教的な基底を成しています。一方で、キリスト教国家は、アニミズムを排除しながらその宗教観を形作ってきました。キリスト教的な宗教観では、人間を他の動植物と区別しており、特に理性があることを根拠として「人間の尊厳」が主張されてきました。欧米社会では、臓器はまだ動いているものの、脳の機能が停止した人を「脳死」とみなして、臓器移植を行うことを積極的に推奨しています。一方、日本では身体が動いている人を「死んでいる」と捉えることへの抵抗感が根強くあります。それは、身体は理性によって動かされる機械ではなく、それ自体に魂があるものだという考え方が染み付いているからに違いありません。このような東西の宗教観(死生観)の違いは、生命倫理の問題への取り組み方にも違いをもたらします。その結果、脳死制度の導入の程度は、日本と西洋諸国で大きく異なっています。
脳死の例では、欧米社会が脳死の人を「死者」と割り切っているのに対して、日本のアニミズム宗教観は判断に留保をとっていました。しかし、日本の宗教観の方が欧米社会と比較して、全ての面において生命を重んじているのかというと、そういうわけでもありません。アニミズムを基底とするアジア文化圏で、中絶やいわゆる間引きなどの幼児殺しが行われやすい事実もあります。西欧で全く子殺しが行われなかったわけではありませんが、現代においても、カトリックや一部の生命尊重派の宗派が根強い国や地域で、中絶自体が法律で禁止されているところは多く存在しています。そして、日本で全く平然と子殺しが行われてきたかと言えば、そうではありません。気が引けたり、悲しみが伴ったりすることもあったはずです。その慰めとなる考え方として、子どもの生まれかわり信仰があったと考えらています。私たちは、一人一人の個別な人間であるというよりも、ひとつの大きなプールのなかから、ある時間だけ生まれ出てきて、死ぬとまた帰っていくようなものだと考えられてきました。そう考えることで、たとえ個人がいなくなったとしても、集団は残るということにつながります。
このように、キリスト教以外の文化圏では、むしろ個々の生命は、アニミズムの価値観のもとに、犠牲となることが多くあります。仏教では人間と人間以外の自然を区別せずともに断絶のない宇宙の一部だと見なしています。キリスト教と比べた場合、仏教、道教、神道のようなアジアの諸伝統は、人間とそれ以外の被造物との間に明確な倫理的区別を立てない傾向があります。
21世紀を迎えた現在、死すべきものとしての人間のあり方が、諸科学において改めて問い直される状況が生じているのかもしれません。「生と死の思想」に親しむことは不可欠な学びに違いありません。
参考引用:東京大学 死生学に関する講義一覧
https://ocw.u-tokyo.ac.jp/course_11318/
|